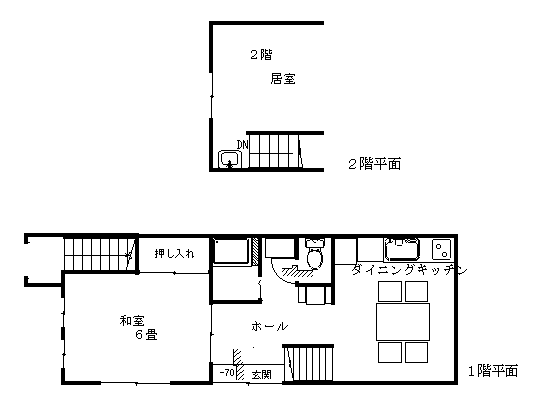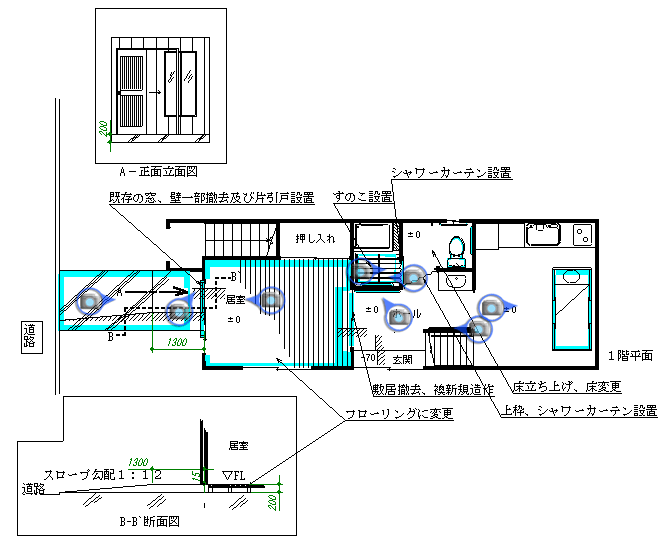| 問題点 |
- 歩行による屋内移動が限界になっている。(転倒頻度が増加している)
- 車いす利用における居住空間(特にトイレ部分)の不適合。
- 既存玄関利用の限界。(駐車場⇔玄関まで歩行していた)
- 浴室内への跨ぎ越しが困難になっている。
- 2階での居住が困難になっている。
|
| 家族・本人の要望 |
余り大掛かりな改修は行いたくない。必要最低限で良い。 |
| 住宅改修の目的 |
自宅内車いす生活を基本として、家屋外へのアプローチおよび車いすからトイレおよび介助歩行による浴室へのアプローチの安定を目的とする。 |
| 住宅改修の場所と内容 |
- 玄関:既存玄関からの出入りを中止。
居室(6畳)の外(駐車場)へ玄関を新設。
スロープ作成し、玄関部分で電動車いす⇔自走車いすへの移乗を行うようにする。
スロープは車いすの脱輪を防止するために外側を高くしている。移乗用に縦手すりを設置する。 - 居室:畳はフローリングに変更し、車いす走行(特に電動)に支障が無いことと、掃除がしやすいようにする。
- トイレ:既存トイレを撤去し、新たに洋式便器を設置。
便器の方向を180度反対方向にする。
高さも便器の下に下駄を付け、7センチ程度高く設定する。
出入り口部分の既存壁を撤去し、車いすでの出入りをしやすくする。また既存の手すりは移設する。
前回設置した縦手すりの一部を撤去し、玄関出入り口へ移設。 - 浴室:洗い場にすのこを設置し、段差の踏み越えをなくすようにする。
浴室折れ戸を撤去し、シャワーカーテンを設置する。
トイレのドア撤去および浴室のドア撤去に伴い、トイレのプライバシーおよび浴室の保温を兼ねてカーテンを設置する。
|
| 支援チームの構成 |
在宅介護支援センターPT、在宅サービスセンターOT、障害者ワーカー、保健衛生部OT、担当保健婦、工務店 |
 図面のこのマークにマウスをのせると実際の写真が表示されます。
図面のこのマークにマウスをのせると実際の写真が表示されます。