住宅改修を行うことによって、本人が家に帰りたいと強く思い、それがよい循環となった
| 基本情報 | |||
| 年 齢 | 74歳 | 同居家族構成 | 妻、長男夫婦とその子供3人 |
|---|---|---|---|
| 性 別 | 男性 | 主介護者 | 長男 |
| 疾患名 | 脳梗塞 | 家屋の所有形態 | 持ち家 |
| 障害部位 | 右片麻痺、失語症状は徐々に改善しつつある | 家屋の建築形態 | 1戸建て木造2階建て |
| 要介護度 | 要介護3 身体障害者手帳1種1級 |
周辺環境 | 山間部、寒冷地、降雪地域、農業地域 |
| 日常生活の状況(改修前の状況) | |||
| 起 居 | 自立 | 排 泄 | 部分介助 据え置き式便器(既存便器着脱)使用。 便器への移乗は妻の介助 |
|---|---|---|---|
| 移 動 | 車いすによる自立移動が主 左足でこぎながら移動 杖、シューホンブレースにて、監視歩行レベル。 |
入 浴 | 介助 息子の介助により入浴の予定 |
| 移 乗 | ほぼ自立 ベッドからの移乗は何かにつかまればできる。いすや自動車などに関しては一部介助。 |
介護サービスの 利用状況 |
改修前:なし 改修後:ショートスティ |
| 実際の改修箇所 |
 図面のこのマークにマウスをのせると実際の写真が表示されます。
図面のこのマークにマウスをのせると実際の写真が表示されます。
|
| 改修前の状況 |
|---|
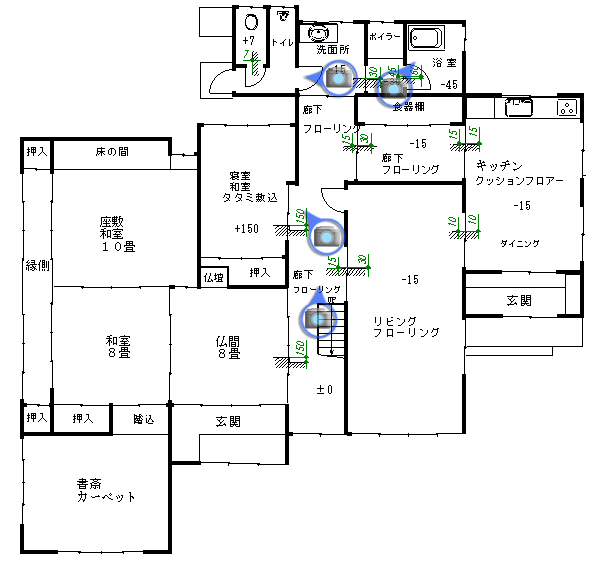
|
| 改修後の状況 |
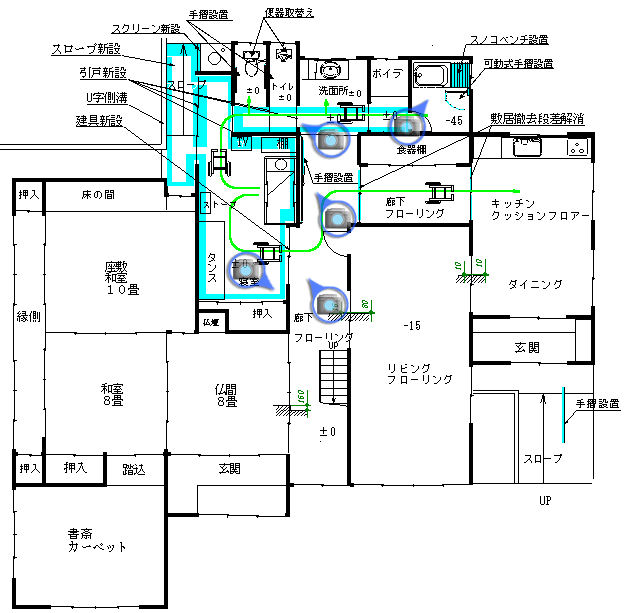
|









| 住宅改修の概略 | |
| 問題点 | 対象家屋は数回にわたり増改築しており、高い段差が非常に多い。 また、建物自体古く、床組みも老朽化していると思われる。 入院生活が長く、リハビリもしたがらず、妻に依存し、自分で何かをしようとしない。 妻の介護負担を軽減しなければ、妻も倒れてしまうかもしれない状況にある。 |
|---|---|
| 家族・本人の要望 | 本人も介助者である妻も自宅に帰りたいと願っており、一日も早く帰宅させたい。 妻の介護の負担を軽減するため、自立できるような改修をしたい。 |
| 住宅改修の目的 | 車いすからの移乗も妻の介助を必要としているが、何かにつかまればできるレベルにある。 本人に自立しようという意欲を持たせるためにも、車いすで寝室から居間、食堂、トイレへの移動をできるような改修を行う。 |
| 住宅改修の場所と内容 |
|
| 支援チームの構成 | 行政担当者、PT、建築士、施工業者 |
| 福祉用具 | |
| 支援前 | レンタル:電動ベット(3モーター) |
|---|---|
| 支援後 | 車いす |
| 改修後の評価 |
| 改修工事を行う前は妻にすべて介助されていたご本人だったが、家を改修するとなった途端リハビリをし始め、杖で歩く練習や階段の上り下りの練習を始めた。 これまで何に関しても意欲を見せなかった本人に、家に帰れるという希望が見えたせいなのだと思った。 今では妻がいなくてもベットから立ち上がり、杖と手すりを使って居間やトイレに行っている。 住宅改修を行うには本当に良い機会に工事することができた。妻は看護疲れから現在入院中だが、本人にとっては本当に良かった。 |
| 残された課題 |
| 課題としては、主に車いすでの生活を視野に入れてプランを提案し工事を行ったため、脱衣室と浴室を除く他の部屋や動線には問題はない。 脱衣室に関してはスペースが狭すぎ、ボイラーをおく位置を検討する必要がある。 また、浴室に関しては、床の段差が大きいためシャワーキャリーでそのまま使用する場合には介助力に頼ることになる。 床の段差を解消するかもしくは浴室全体の改修をも視野に入れた改修を検討する必要がある。 屋外へは現在杖と手すりによる移動に対応したスロープの仕様になっているが、車いすになった場合、南側に直接出られるようなスロープや、段差解消リフト等の設置をも含めた移動方法を提案していく。 |
